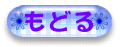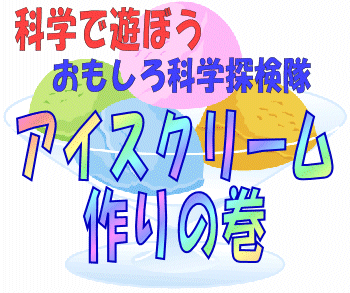
|
本日は、支えあい連絡会「地域づくり分科会」の行事。 「おもしろ科学探検隊」のご指導で 『科学で遊ぼう! 〜アイスクリーム作りの巻〜』 を開催しました。 この「探検隊」は、地域で活発な多世代交流活動をしていらっしゃる団体で、開催行事には毎回子供から大人まで参加し、自然と多世代の交流が実現していると言う羨ましい団体です。 今回の目的も、子供と大人が「アイスクリーム作り」に熱中している間に、年代を超えた結びつきを作ってしまおうとの魂胆でした。(平成18年7月2日) |
 隊長さんから説明 |
 班分け |
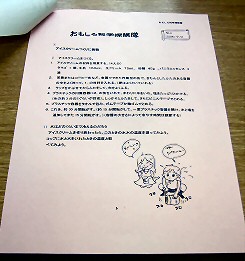 |
道具類 |  |
 |
 さて会場では、小さなカンカンにアイスの材料(卵と牛乳と砂糖と香料)を詰める作業が始まりました。講師の関口秀夫さんから『一生懸命に作ると美味しいアイスが出来ますよ』と説明があると、材料を量る目つきも真剣さが加わってきました。
さて会場では、小さなカンカンにアイスの材料(卵と牛乳と砂糖と香料)を詰める作業が始まりました。講師の関口秀夫さんから『一生懸命に作ると美味しいアイスが出来ますよ』と説明があると、材料を量る目つきも真剣さが加わってきました。
|
||
 |  |
 |
 次に、大きなプラスティックの容器に氷と塩を入れ、その中に頑丈に封をした先程の小さなカンカンをいれました。塩の量が生半可ではありません。この塩が温度を下げるとは未だ誰も信じていません。この大きなプラスティック容器も頑丈に蓋を止めてタオルで巻、転がす準備が出来ました。
次に、大きなプラスティックの容器に氷と塩を入れ、その中に頑丈に封をした先程の小さなカンカンをいれました。塩の量が生半可ではありません。この塩が温度を下げるとは未だ誰も信じていません。この大きなプラスティック容器も頑丈に蓋を止めてタオルで巻、転がす準備が出来ました。
|
||
 |  |
 しっかり漏れないように! |
 3〜4人のティームに分かれて20分間、床の上をゴロゴロ転がしあいました。中には塩水が漏れて来て応急手当が必要なティームもありました。途中でプラスティックの容器の蓋を開け、温度を測りました。何とマイナス16度を示しています。信じられない低さに驚きました。氷と塩を追加して、更に20分転がしあいました。
3〜4人のティームに分かれて20分間、床の上をゴロゴロ転がしあいました。中には塩水が漏れて来て応急手当が必要なティームもありました。途中でプラスティックの容器の蓋を開け、温度を測りました。何とマイナス16度を示しています。信じられない低さに驚きました。氷と塩を追加して、更に20分転がしあいました。
|
||
 |  |
 |
 緊張の一瞬です。小さなカンカンを開けると、黄色みを帯びた柔らかい物質が円筒状に固まっているのです。信じられない子供達(大人も)は中を覗き込みます。紙コップに入れてもらってスプーンで口に運んだ子供達、『ウメー』。全ティーム成功でした。
緊張の一瞬です。小さなカンカンを開けると、黄色みを帯びた柔らかい物質が円筒状に固まっているのです。信じられない子供達(大人も)は中を覗き込みます。紙コップに入れてもらってスプーンで口に運んだ子供達、『ウメー』。全ティーム成功でした。
|
||
 |  |
 |
 |  |
  |
 転がし作業の最中、集中心を無くしそうな子供には、大人がそれとなく引き戻したり、子供同士で牽制し有ったり。最初は仲間に加わらず遠くから眺めていた子が、最後には中心人物になっていたり。地域社会の縮図を眺めている感じがしました。
子供から大人まで一緒になって作業を進めると言った行事が少なくなった現在、貴重な催しだったと思いました。アイスは冷蔵庫から出てくる物と思っている子供達、科学離れが話題になっている昨今、少しは引き戻せた様な感じもしました。
転がし作業の最中、集中心を無くしそうな子供には、大人がそれとなく引き戻したり、子供同士で牽制し有ったり。最初は仲間に加わらず遠くから眺めていた子が、最後には中心人物になっていたり。地域社会の縮図を眺めている感じがしました。
子供から大人まで一緒になって作業を進めると言った行事が少なくなった現在、貴重な催しだったと思いました。アイスは冷蔵庫から出てくる物と思っている子供達、科学離れが話題になっている昨今、少しは引き戻せた様な感じもしました。◆参加者、28人(内大人10人) ◆お手伝いは、「地域づくりの会」の皆さんでした |
||
|
(後日談)終わると床が白い粉で覆われていました。舐めてみると「ショッパイ!」。
そうです冷媒となった塩が漏れてきて乾燥したのです。モップ掛けでアイスが汗になってしまった職員さんゴメンナサイ。(取材 広報Neri) |
||